|
己を己と成した世界を創り上げた核が、消滅した。 それでも、変わらず時は過ぎ、世界は回る。 だったら………あの世界は、何だった? 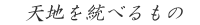 − 3. 墜星 − まず、失って初めて感じたのは、虚無感でも喪失感でもなく。殺伐とした、世界が一変したような視覚の変化。 軍師や、もう居はしない彼以外の従者と相対してるのは、確かに自分で。 それでも、それは感覚を伴わない。 フィルター一枚で隔てて、どこか遠くからそんな自分を冷静に見ているような……そんな感覚。 まるで……全てが幻のようだと。 現実味を帯びない感覚で、漠然と思うのだ。 触れようとして伸ばした手が、直前で止まる。 先のソニエール監獄への出立する前に見た時には、確かにあった名が……今はない。 標された名の数は変わらないのに、その中にただひとつの名が見つからない。 ただ漠然と、何故だろうと思う。 彼だけは、何があっても絶対に僕の傍を離れないんだろうなと、なんの保証もないのに当然のようにそう思い込んでいた。実際には、今彼は傍にいないのに。 石板前で躊躇い留まっていた指先を握り込んで、踵を返す。―――と、訪れた時にはなかった石板守りの少年の姿が目の前にあった。 「………ルック」 「用が済んだんだったら、さっさとどいてくれない」 冷たいとも取れる言い様に漸く、今自分が立ち尽くしていた場所がルックの定位置だという事に気付く。 「あぁ、ゴメン」 数歩脇へ移動すると、当然といった態で小さな躰はその場に収まった。 ルックがこうして守りに着くという事は、夜が…明けた? たったひとつある小さな明り取りの窓から外を見やれば、白々と輝く空が垣間見えた。まだ、明けきってはいないようだ。砦内も、ざわめき出す前の独特な雰囲気に包まれている。 そういえば……僕はいつからここに居たんだっけ。まだ暗かった事しか覚えていない。ぼやける記憶に、僅か頭を振る。 最近、感覚が麻痺している自覚は然りとあったけれど。 夜が明けたのなら、己に課されている責を負わなければ…と、視線を室内に戻した所で小さな石板守りの姿をその内に捕らえる。 「食事…取った?」 ゆったりした法衣の上からも窺える細さに心配になりぽそりと問えば、 「あんたには関係ない」 言葉だけが返ってくる。 「もっと…ちゃんと、食べないと」 いざという時に動けなくなるだろ、と言うと、深い翡翠が漸くこちらに向けられた。 「………今のあんたに、そんな事言われたくないよ」 少なくとも僕は、あんたより睡眠も食事も摂ってると思うけど。そう口ほどにものを言う瞳に射竦められて、身動きさえ取れなくなる。 「従者が居ないと、あんたは何も出来ないの」 ルックの遠慮も気遣いも一切ない台詞に、身体が強張るのが解った。 何も知らないくせに―――そう言うのは、簡単だけど。ルックにそう言うのは、違う。 それは、単なる甘えだ。 「違うよ、ルック。摂らないんじゃなくて摂れないんだ」 「それが解ってて、解決を試みないって?」 「忘れたくないんだ」 そう言うと、ルックの綺麗な柳眉がぴくりと僅かに上がった。 「グレミオを亡くしたのは僕の過ちだ。グレミオの甘えを許したから」 その報いだろうと…思った。 「幾ら従者でも、いや、従者だからこそ軍主としてはっきりとした判断を下すべきだった」 だから―――。 「罰、なんだよ」 ………これは。 「そうすれば、何が変わるの」 「……えっ?」 「あんたがそうする事で、何かが変わるのかって聞いてるんだ」 要するに―――と。 「ただの自己満足じゃないか」 事実をありのままに突き付ける言葉は刃と同じで、鋭く胸を抉る。 「――あんたは今、何をやってるの」 「……ルック」 「あんたが今やってるのは、何なのさ」 冷たい怒り―――。強い瞳。 痛みさえ感じるそれに、だけれど視線を逸らす事なんて出来ない。ただ、強く惹き込まれる。 「そんな事も解からないくらい呆けてるんだ」 誰も彼も…どこか労わるような、哀れむような、居た堪れなくなるようなそんな表情でしか僕を見ない。その中において、ただ、この少年だけが、そんな感情とは掛け離れた視線を向けてくる。 「―――あんたがやってるのは、戦争だろ。人の生命が紙屑みたいに扱われる場所だよ。誰が死んでも文句なんていえるようなところじゃない。あんたは、それが解かってるんだと思ってたけど」 「…………悲しむ暇もない?」 「僕が言ってるのは、今のこの状況でそれをやる事自体が間違ってるって事だ。悲しむのは何時だって出来る。今やらなきゃならない事をやるべきだ」 彼の言っている事は、これ以上もなく正しい。 だけれど、正しいが故に淡々と事実を告げてくる少年が、刹那酷く憎らしく思えた。 どうしてこんなにも、冷たいまでに突き放す? 心の内が、凍るのを感じる。 それを彼に向けるのは違うとは解っていても……制御の箍が、外れる。 一気に、視界が感覚が、そして感情がクリアになる。 「君に…何が解るって?」 グレミオはずっと僕の傍に居て、そして惜しみない愛情を与えてくれる、ある意味肉親よりも近しい人だった。子供の頃は、それこそ世界の中心で。そうあるのが当然だと…そう信じていた。 その人が、その世界が…己の判断の甘さで一気に瓦礫した。 「君に、何がっー」 「そんなの、解る訳ないだろ」 激昂する己とは逆に、ただ静かに呆れたように返される。 「尤も、その必要性も感じない」 それはあんたの内の問題じゃないか、ときっぱりと言い切られ。 「そもそも、解って欲しいなんてそんな甘えた事、あんたは思ってやしないだろ」 ルックの台詞に、驚愕する。 「その痛みは、あんたにしか解らないんだよ」 誤魔化す事なんてないじゃないか―――と。 隠す事なんて、しなくていい―――と? 「あんたが今、あの従者にしてやれる事なんてそのくらいしか、ないんだよ」 ―――この子供は。 微かに震える拳を、力の限り握り締める。ぎゅっと閉じた瞼の裏が熱を持ち。それでも、自然、零れそうになる嗚咽を…噛み殺す。 溢れた何かが、頬を伝う。 肩が小さく戦慄くのだけは、どうしようも出来なかったけど。 「大概、意地っ張り」 呆れた風な声音を聞きながら、いっそ唇を噛む。それ以上、ルックは何も言わなかった。ただ、黙ってその場に立っていて、いつものように無表情に真っ直ぐ前を見つめていた。 だから。 ただ、とうとうと零れ落ちるに任せて、声もなく泣いた。 それは……グレミオの死に、初めて流した泪だった。 薄っすらと、砦が朝を迎え。 ざわざわと活動を始めた人々の息吹で、目覚める。 「迷ってるんだったら、いくらでも立ち止まって考えなよ。それでも答えが得られないんだったら、取り敢えず前を向けば? 後悔ばかりしてるよりは余程、建設的だろ」 ひとしきり涙した後、ルックは呟くようにそう言った。 歳に合わない悟ったような台詞に、彼は今までどんなモノを見て何を思ってきたのだろうと不思議に思う。それとも、何も知らないから言える台詞なんだろうか。 どちらにしても、僕をこの世界に戻してくれたのは目の前の少年に他ならない。 「ルックは…凄い」 本心思ったままを言ったのに、それに返されたのは肩を竦めるという所作と、 「煽てたって何も出ないよ」 という手強いひと言。 「煽ててるつもりなんてないけど」 「僕はあんたに何かをしてやったつもりないよ」 そう言って、口許に軽く笑みを刷く少年に。 「ルックって自信過剰な割に謙虚だよね」 「自信、過剰?」 「あー、ゴメン。過剰ではないか」 ピクリとあがった眦に慌てて訂正する。と、当り前だろうと返された。 「僕はないものをあるなんて面倒な事言わないよ、逆はあってもね。出来もしない事を求められるなんて真っ平だ」 あまりに彼らしい言い分につい笑みが漏れる。そうだ、ルックは常に自然体で必要以上に自分を誇張したりしない。 「うん、でも僕はルックがそうして見ててくれれば、それだけでいい」 思ったそのままを告げた。 「ルックがいてくれて良かった」 「……僕には不本意でしかないけど、ね」 うんざりした様を隠しもせずに溜息を吐かれて、溢れるのは怒りより苦笑だ。 「だけど、最後まで見ててくれるんだよね」 「あぁ、今度呆けてたら切り裂いて目を覚まさせてあげるよ」 いっそ鮮やかな笑みで宣言された。 きっと、ルックの迷いのない翡翠が、視線を逸らしたくなる認めたくない事実のみを紡ぐ言葉が、前へと進む機動力になる。 躊躇いを四散させる、風になる。 それはこの先僕が進み続けるのに、一番必要なものだ。 だから、きっと彼が見ててくれれば立ち続けていられる。 冷たい石の表面をそっと指先でなぞる。 伝わってくるのは、冷たい石の感触とそれの持つ本来の温度。だけれど、冷たいとは思わない。 「頑張るから………見ててくれ」 かつてはあり、今はない名に、そっと祈った。 …… to be continue |
back ・ menu ・ next