|
それに気付いたのは、その波動が誘惑にも似た色を含んでいたから。 気紛れのように触手を伸ばしてきたのを、己が身を守る自衛の風がそうと悟らせない内になぎ払う。 「バカにしてんじゃないよ」 宿主の意を反映しないその程度の力量で、僕を捕らえ呑めるとでも思っているのか。 ふっと、そのまま波動の軌跡を追う。 あの軍主は…ソウルイーターを御しきれるんだろうか。 御せなければ、アレは宿主でさえ容易く喰らう。 それ程に、残虐な、貪欲な神なのだ。 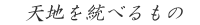 − 4. 闇の息吹き − 偵察・視察・各地の有力者への顔繋ぎ。 ようやく形になり始めたばかりの解放軍の土台の確立に伴う、人員やら物資やらの確保と。 そして、連日早朝から深夜に及ぶ軍議。 解放軍への協力・賛同者は、軍ではなくサクラ・マクドールというただひとりの人物に傾倒しその志しを申し出る者の方が圧倒的に多い。 ―――ときては、軍主であるあいつに暇などある筈がないだろうに。 それでも、軍主は毎日毎日石板前へと訪れる。 だから、 「暇なのか?」 そうじゃないと知りつつも訊ねてしまう。 「な、訳じゃないけど」 苦笑混じりで言う姿は、その穏やかな笑みだけを見てると、とてもじゃないが一軍を率いる軍主さまには見えない。 解放軍へと身を投じる者達は、日に日に増しゆく。 こいつの何に賭けようと思ったのか。 まったく持って解らない。 「好き…なんだよね」 「はっ?」 「この空間」 何も纏う必要がないから、凄く楽だと。 「ま、確かに僕はあんたに何かを求めてる訳じゃないしね」 僕がこの場に居るのは、ただ―――それが師の、星の意思だったから。 だけど、僕の言葉に返されたのは静かな笑みだ。 「そういう意味じゃないけど」 酷く穏やかに微笑む様に、わずかに目を細めた。 この男の言動は、たまに僕の思考の範疇を超える。それ即ち、全くもって理解不能ってヤツだ。 どうでもいいけど、と視線をそらしたところで、ふっと気付く。 「明日の昼辺りたりから、雨になるよ」 窓から吹き込んできた風が、仄かな湿り気を含んでいた。 風の軌跡を追っていた視線の隅に、ぴくりと身じろぐ軍主の姿が入り込んで。 「雨、嫌いなの?」 知らぬ間に、問うていた。 「……どうして?」 そう思うと聞かれて、首を傾げるのはこちらの方だ。 「何だってそう思われてないと思うのさ」 雨の日には、遠征はない。どころか、己の部屋から出もしない。どうしても外せない会議の最中陰鬱そうな顔で、それでも笑って見せている。雨の気配がすると何気なく告げる度、竦んだ身体に気付かない程、鈍くはない。 そんな様を見せられて、どうして雨を好んでないと思えるのか教えて欲しいくらいだ。 「雨を呼ぶ風は、優しいのに?」 それだけで、雨は数少ない好ましいものと感じてさえいる。 それに。 僕が初めて見た世界は、雨の中だった。 若葉を打つ雨は、穢れを取り込んで空気を清浄化する。世界の彩りを更に鮮やかに映し出す。 いわば、それが僕の世界の始まりだった。 だからこそ、雨を呼ぶのも去らせるのも風だという、ただそれだけのことがただ単純に嬉しかった。 「……ルックは、雨好きなんだ」 「あんたは、雨あがりを知らないの?」 それがもたらす、命の根源という彩りを。 「雨が嫌いだっていうんだったら、待ってればいい」 「…何を」 訝しげな視線を向けてくる男に、 「知らないの?」 と楽しさも手伝って問うてみる。 「雨はいつか止むんだよ」 大きく瞠られた黒曜の瞳が可笑しくて、ちょっとだけ口許が綻んだ。 宵も更け、砦は寝静まる。 ぽつりぽつりと要所に点在する警備兵でさえ、その眠りを妨げることなく存在する。 ここ数日、小さな小競り合いは続くもの、戦そのものに然したる進展はない。このままの状態がいつまで続くのか、先が見えなくてうんざりする。 そろそろこの砦での生活にも慣れてきたとはいえ、毎日毎日、同じことの繰り返し。大きく溜息を吐き出して、石板を離れた。 そのまま、人気もなくなった頃合いだろう風呂場へ足を向ける。 風呂が出来たばかりの頃、一番混む時間に入ってしまったことがある。やたらと五月蝿かった上、好奇の視線に晒されて、二度と入るもんかと、あの時は心底後悔した。風呂に入るというより、人に塗れるって感じで、余計疲れた。 このくらいの時間なら空いてる、という風呂職人の進言もあって、大抵この時間に風呂を使うようにしていた。 薄暗い廊下を抜け、角をふたつばかり曲がれば風呂場というその時。 さわり、と。 どこからか巻き上がった風が、髪を揺らし、頬を擽った。 「……?」 常なら気にならないそれが、僕の内の何かに触れる。急かされるように視線を巡らせようとし、何の前触れもなく身を襲った衝撃に暫し息が止まった。 「な、ッ」 衝撃の元は、腕を掴まれた所為。そうした相手の容貌は逆光で窺えず、無駄に大きな男だという事しか知れない。 恐怖より何より、周囲の気配さえ感じ取れなかった事実に、己の迂闊さを呪う。 暗殺者か、と身構える暇もなく、廊下に面していた空き部屋の中へと勢いよく引き込まれ、何の準備もないままにどさりと投げ出され。躰に衝撃が走る。 「ーッ、」 石床の所為で、打ち付けたあちこちに感じるのは生半可じゃない痛み。 どこのどいつだ、と確認する為に振り仰いだ視界に入ってきたのは、大きな影。その勢いのまま、のし掛かってくる。 冷たく硬い床に躰を抑え込まれ、詠唱をする間もない。 押し退けようと腕を振っても、ビクともしない。 頬を掠めた熱い息が、首筋に触れた―――瞬間。 「痛ッ、」 熱さとも痛みともいえる感覚に、咄嗟噛まれた、と思った。 が、痛みの後に、ねっとりとした舌の感触が続く。 肌が、ざっと粟立った。 荒い息。 法衣の上から、慌しく弄る手。 その手が、忙しなく腰帯を解くのに気付き。 少なくとも、これが拳や刃物での暴力でないことを知る。 この行為にどんな意味があるのか…なんて知らないが。 けれど、酷く屈辱的な扱いをされている事だけは解る。 相手の熱を増す呼吸とは逆に、どんどん冷えてゆく己の中の何かを感じる。 「………消しちゃって、いいんだよね」 そう、ぽそりと言葉にして確認する。 例え相手が誰であろうと。自分の意志を無視し、屈辱を強いる事など許さない。自分が自分であろうとするのを阻む存在など、云うに及ばず―――。 胸元に落ちた男の唇に嫌悪を感じるより先に。 激する感情が発露するように、己より溢れ出すそれを制御する気など毛頭なく。 身の内から迸る風の刃が、己を組み敷く男に躊躇う事無く襲い掛かる。 「――――――ッ!」 轟々と唸る風と、くぐもった呻き。 身を抑える圧迫感がなくなったと同時に、生温かな体液が水音を伴って降り掛かる。 しとどに身を染めるのは、暗く紅い血色だと。 嗅覚を迷わす生臭さは人の身の内を巡るものだと、見ずとも知れていた。 「………気持ち、悪い」 そうっと持ち上げた掌には、見知らぬ男の命がこびり付いていて。 赤い、朱い…命の紅。 何だって戦場でもないこんな場所で、こんなモノを見る羽目にならなきゃならない。顔が歪むのが、自分で知れる。 「くくく……」 知らず喉元にせり上がってくるそれが、何なのか。 そんな事、知りたくもなかった。 …… to be continue |
back ・ menu ・ next