|
人通りの少なくなる時刻までには、仕事を切り上げなさい。 と、通達してきたのは軍師その人で。告げられた時には、呆気に取られた。 何を言っても何をしでかしても、それが許容できる範囲内であるのなら、こちらの領域内には踏み込まない姿勢を貫いていたその人だったから。 柔らかな表情ながら、 「寄せ集めの軍なれど、人が集まれば法が必要だろうという進言がありまして」 毅然とした態度で告げてくる。 確かにここ最近、砦には多くの宿星やら兵やらが集まって来てはいる。軍師の言うことも解る。 が、違和感が付き纏う。 「仕事の時間を決めるのも、その内のひとつだって訳?」 「貴方が石板前から自室に戻るのは、既に子どもが出歩く時間ではない、でしょう」 軍師の台詞に目を眇め、言葉もなく口を閉じる。 この男が自分を子どもと評するのは初めてだ。 以前、人を外見で判断すると痛い目を見ますからね、と言っているのを耳にしたことがある。 魔法兵団長へ命じられた時も、魔法という特殊能力部隊なのだから実力前提での人選だと言い切っていた。だとすれば、軍師が子どもと言っているのは、この外見にってことに他ならない。 「……誰の進言か、訊ねていい」 その唇から発せられる名が誰のものなのか、聞かずとも知れていた。 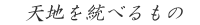 − 6. 死と屍 − 軍律なんて、僕には関係ない―――とは思うものの。 長と名のつく位置に身を置く者としては、容易く破る訳にもいかず。 「余計なことを」 イライラしつつ認めた姿に開口一番そう言った僕に、それを覚悟していたのか軍主は静かに微笑んだ。 「こうでもしないと、僕個人の言うことなんて君は聞いてくれなかっただろ」 返ってきた言葉に口を噤む。 確かに、個人的に命じられていたら拒否してただろう。星の天辺に立つ者とはいえ、星の指し示す先へと導く者の意を汲めなければ、そうする必要性すら感じないのだから。 こいつが今の立ち位置に在るのさえ、その道への最短距離だからだとしか僕は考えてない。根本的に他の星々とは立ち位置が違っているのだ。 小さく溜息を零すと、軍主はその内を窺わせない種の笑みを浮かべる。 「それに軍律は、やっぱり必要だよ」 ますます人は増えるだろうし、今現在でさえ小さないざこざはあちらこちらで起こっているしとの言は頷くしかない。兵たちにも大小様々なストレスはあるだろう。尤も、律如きで抑え切れるのかどうかなんて、考えるまでもないだろうけど。所詮そうするのは、個である自身なのだから。 「……ま、ないよりはって程度か」 「厳しいね」 くつりと、喉を鳴らして笑う。その様に、違和感が付きまとう。こいつは…こんな仕草をするヤツだったろうか。 「全てを護るなんてことは、所詮無理なんだから。だったら、せめて身近に置く人たちだけでもってそう思ったんだよ」 いわゆる、自己満足に過ぎない―――などと、自虐的に笑う男の姿に。 諦めたくなくて。 だけど、諦めない訳にはいかなくて。 だから、この男はこんな風に笑うんだろうか。 知らず、眉間への皺が増えるのを感じた。 「暫し暇を貰うよ」 唐突に部屋を訪れ開口一番そう言い放つと、切れ者と誉れも高い軍師の驚いた顔を見る事が出来た。珍しい…と、思いながらもこちらは顔には出さない。 「今のこの時期に、ですか?」 思慮深い眼差しが、こちらの真意を窺うように向けられる。全てをとまではいかないが、この軍師はその瞳で粗方のものを暴き出すんだろう。 「師匠から帰還を命ぜられた。あの方は個人的にこの戦に思い入れがあるから、この帰還は今のこの時期にこそ必要だって事だ」 淡々と告げると、マッシュは僅かに逡巡を見せた。 戦力の低下を危ぶんでいるんだろう事は、容易に知れる。 「あんたは、あいつが宿しているモノを知っているだろ」 「……真なる紋章、ですか」 ひとつ頷いて肯定とする。 「この地からは随分離れるけど、ハイランドって国がある。あそこは真なる紋章のひとつを貸与されるほどハルモニアと親交が深い」 ハルモニア―――その国名が示すものを知らない者は、皆無に等しい。 「進軍の恐れがあるとでも?」 間にデュナンを挟んではいるが、かの国の紋章術の進み具合は計り知れない。本国からは無理でも、ハイランド辺りからなら大軍勢を一斉に転移させるなどといった高等術が未だないとは言い切れない。 今現在この地には、真が集まり過ぎている。基盤自体が揺らぎ始めた帝国と、勢いはあっても敵が二つになれば対処しきれる筈もない解放軍から隙を見て―――なんて事は、容易だろう。 「有り得なくはないだろ」 「……あなたが帰還したところで、それを食い止められるとでも?」 「さてね。でもそれが師の言いつけならやるよ」 だけど、自信がない訳ではない。勿論、師の援護とこの身を構える風の封印が解かれている事、が前提であればこそ、だけど。 「了承しました。無事でのお帰りを待ちましょう」 帰ってきたら魔法兵団の編成をお願いしますから、と去り際に面倒な仕事を言い付けてくるのに。 「………頭に入れとく」 面倒臭いのを隠しもせず頷く。 「尤も、そんな余裕があれば、だけどね」 相手が相手なだけに、結構な重労働を強いられるのは嫌というほどに解っている。 「この時期に…と言ったのは、そう意味ではなかったのですがね」 転移間際、ぼそりと聞こえて台詞に思い至る事柄もなく。だからそれは、ただ首を傾げさせる代物でしかなかった。 人も獣も魔さえ寄り付かない、孤高の塔へと帰還した際、星の流れから目をそらすことなく師が告げたのは。 ―――向かい打って殲滅、もしくは退却させろ。 「軽々しく言ってくれる」 相手が彼の大国だというにも拘らず、臆した風もなくそう課してきた。 わずか溜息をつき、肩を落とす。 風を介して見た平地には、大きな魔方陣が描かれ、先導隊らしい一陣が術をくみ上げている最中だった。大掛かりな術なのは、練られた魔力の大きさが物語っている。 風を介しているにも関わらず、押し止められそうになる。 「転移間際の不意を突けば、容易いでしょう」 師の言を思い返す。 「確かに、」 無防備、だと目を細める。 己等へと対抗する力など有り得ないとでも思っているのか。 それとも、これだけ大掛かりな術を行使していながらも、それが近隣諸国に筒抜けだという認識もないのか。 一応といった感じで周囲に張り巡らされた結界は、その内で発動されている術を隠せるだけのものではない。 それとも、脅威として力を誇示しておきたいのか。 ふんと鼻をならし視線を巡らせたところで、ふっと。 「……アレ、は」 視界の内に映える青を拾う。 それを認めた刹那、どくんと、鼓動が跳ねた。 その揺るぎない地位を示す青い法衣は、ハルモニア神聖国のもの。小さな身体にそれを纏う少年の面は。 「ーーーーーーーーーーーッ?!」 同じモノなど、ない…と。 あってはならないのだと、そう思って全てを破壊し尽くしてきた筈なのに。 息をのむ。 動揺を、自制しきれなかった。維持していた魔力が、感情の波に揺れ。その気配に気付いたのか、蒼い瞳がひたりとこちらを捉えた。そして、大きく瞠られる。 「…君は、誰だ」 驚愕に歪められた顔。 それを、僕は知っている。 知っては、いるが。 コレは……ナンだ? 己ではありえないモノが、己と同じ疑問を抱き同じ問いを掛けて来る。 驚愕に瞠られた空より青い瞳が―――視界を埋め。 コレは、誰? コレは……なに? 同じじゃない? 違う? 何が、どこが? ボクが? こいつ、が? ――― ち が う ッ! 一斉に、雪崩れ込んでくる記憶の数々。 刹那、視界を埋めるのは、己でありながら己でないモノの骸にさえなれないモノ。 封印球という檻から解き放たれ、ただの土塊に還るだろう、肉片。 「ぁ、っ………ぁ」 それらは、禍々しい創りモノの成れの果て。 制御しきれず溢れ出でる力と、崩れ落ちる白亜の神殿。 「ーーーーーーッ!!!」 咄嗟、遮断した記憶の淵で。 カチリ、と解かれた枷の音を感覚が捉える。 と共に、身の内より抑え切れない風が、抑える術もなく轟々と解き放たれた。 咽るような血の匂いを運んでくる風は、どこか生温かい。 地に描かれていた筈の魔方陣内に所々に横たわるのは、血に塗れた屍ばかりで。そこには見られない青い法衣に、アレはどうやら逃げたらしいと知る。 「……」 小刻みに震え続ける手を、そうとは気付かずにぎゅっと握りこんだ。 ―――刹那。 「よく退けましたね」 背後から掛けられた声は、聞き慣れもの。 「レックナートさま……」 名を呼ぶだけで、返す言葉もなく俯く。 感じなれた師の気配は、ただ優しい。だけれど、その優しさは……どこか冷たく。 結果だけを見れば、師に言い付けられた通りのことはこなせた。 だけれど。 唇を噛み締める。乾いた唇に小さく痛みが走った。 「………アレは」 喉が渇く。 気管を過ぎる酸素さえ、痛みと感じる程。 訊きたくは、ない。だけれど、訊かずにはおれない。 「アレは…何なのですか」 全て滅したと思っていた。あの、神殿を半壊した内に、全ての紋章の保管庫があったのだと、そう信じていた。 「アレは、土を宿す為に創られたモノです」 宿す為? 保管庫では…ない? 「いえ、あなたと同じモノです。が、紋章の属性という事です」 土の紋章は、全てを在るがままに受け入れる。 風の紋章は……気紛れで留まることを良しとしない。傍に置き留めようとすれば、常に何かに縛り付けておかなければならない。だから、無理やりに肉体と融合させた? 「火の気性は荒く、その気性故に過去ハルモニアは火を奪われました」 同時期に同場所で存在を確認された研ぎ澄まされた雷は最早鳴らず、常に流れる水は今は行方さえ知れない。 「………アレは、僕を知らなかった」 それ即ち。 神殿のあの場所で育った訳ではないということ。 同じモノでありながら、全てが同じではないということ。 存在の理由を与えられながらも、これ以上もなく滑稽で愚かな―――人形。 指先が、未だ止まることなくカタカタと小刻みに震える。 「まだ、貴方には……早かったようですね」 そう、何の前触れもなく額に触れた冷たい指先が、身を取り巻く真なる力と漠然たる不安を押し込んでくる。 触れただけの指先から伝わる圧迫感はなく。 ただ、カチリと。 微かな音がどこかから響いてくるのだけを感じた。 …… to be continue |
back ・ menu ・ next