|
ソウルイーター。 それ即ち、生と死の紋章。 その言葉の意を知らない訳ではなかったけれど。 親という名の自己を確立させるのに欠かせなかった存在を殺め、たったひとりで永い刻を駆け抜けた親友を喰らった、その時。 そんな上辺だけの言葉の意味を知っていたからといって、どうにも出来ないのだと思い知った。 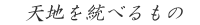 − 7. 刻を知る者 − がらんとした石板の間に足を踏み入れて。 守人がいない状況を目にする度、胸が空虚で満たされていった。 レックナートの許への一時的帰還を許可した―――という軍師の前で、気付かれないように拳を握りこんだのは十日前。 どうして、と口を突いて出そうになった言葉を、唇を噛むことで飲み込んだ。 この軍師が許したというのなら、それは必然だったということ。それくらいは解っている。自らの信念を覆すほどに、誰よりもこの戦争に思い入れがあるのは、恐らくこの軍師なのだから。 それでも。 「…………こんなに堪えるなんて、な」 居場所が、ない。 そんな足許が不安定さを覚えるような感覚に苛まれる。たった一人の少年の存在を、どれ程拠り所としていたのかが知れる。 「情けない」 くしゃりと髪を掻き上げて、自嘲気味に零す。 結局、有難いことに、魔法兵団長を欠いての大きな戦はなかった。 ―――ただ。 大きな魔力の余波を感じた、との報告はもたらされた。この地より遥か離れた場だったらしく、直接的な弊害を被ることはなかった。 何が理由で、何があって、誰が携わったのかといった詳しい内容さえ知れなかったが。 マッシュはその報告に僅か目を開いたが、ただそれだけだった。 軍師の部屋か、石板前か。 ルックが帰還した後、一番に訪れるのはどちらかだと考えていた。 基本的に砦内に居る時は、マッシュが傍にいるのが当然だったから、それこそ僅かながらも空き時間があれば、石板前へと足を運んでいた。周囲が五月蝿いから、日付が変わる頃には自室に戻らなければならなかったけど。 「……いつ帰るんだろう」 既に十日ばかり経つ。 グレミオが逝ってから、こんなに長い時間傍を離れてる事がなかった所為か、不安を拭いきれない。 仕事で帰ったのだと、マッシュは言っていた。 もし仮に、その仕事で彼の身に何かあったのだとしたら? だから、帰還が遅れているのだと…したら? 埒もない想像にぞくり、と悪寒が走る。 ざわざわと、騒ぐのは身の内に巣食う神か、それともただの錯覚に過ぎない程度のものなのか。 気休めに過ぎないだろうとは思いながらもきつく巻いた包帯と、その上の厚い手袋に包まれた右手にぼんやりと視線を向ける。 もし、錯覚ではなかったら? ルックの居ない今、僕ひとりで抑える事が出来るのか? 「ーーーッ、」 抑え方なんて知らない。 抑えられるとも、思えない。 だけれど……そんな事、誰にも言えよう筈もない。 ルックが教えてくれたのは、たったひとつ。 『それを御するのも御せるのも、君だけだ』 そんなこと、解っている……けど。 頭のどこかで、酷く冷静な己が無理だと、そう囁く。 だって、君が居ない。 声が聞けない。 なのに―――僕は、何の為に、どうして、こんなところに居る? 護りたいもの、護るべきもの、護らなければならなかったもの。 その内の幾つを呑み、どれ程を喰らったのか。 「ールックッ」 恐怖が混乱に。混乱が困惑に。 抑えられない。 気が昂ぶる。 ひた隠しにしてきた感情が発露、する。 隠していた…? 「……僕、は」 否、そうじゃない。ただ、気付かないようにしていただけだ。 気付いて、そして、愕然とする。 「ルック、」 あの小さな少年、たったひとりに僕がどれだけ依存していたのか。 数日傍に居ないだけで、こうも容易く崩折れてしまう程に。 「僕は……ッ」 だから―――。 不意に感覚に触れた魔力の波動に。 頬を掠る柔らかな風に包まれ、ゆらりと現れ出でた華奢な体躯に。 かつんと、石畳に撥ねて響く硬質な靴音に。 緩く伏せられた瞼が徐々に開かれる、そんな様に。 目の前に、傍に居るその確かな存在に―――昂ぶっていた気が、嘘のように沈静化していて。 泣きたくなるくらいに胸が痛くなった。 「……おかえり」 石板前で迎えた僕の姿を目にして、驚いたように翡翠が瞠られ。 「………」 次第に、言葉もなく眇められる。 「「……痩せた?」」 声が重なる。 僕は呆気に取られ、ルックは不機嫌そうに眉間に皺を寄せた。 留守中、僅かながら変動のあった石板をじっと見上げる守人。 窺い見える相変わらず綺麗な横顔に、少しばかり顎の辺りが鋭角になったと感じる。成長の為か、はたまた痩せた所為かは解らないけど。 一心に石板を見つめる瞳に、僕の存在は入っていない。 それにムッとしたのか、ホッとしたのかは自分でも判断しかねながら、視線を足許へ落す。 「……………僕は」 思わず、感情が堰を切った。 「僕は………怖いのかも知れない」 弱点を曝け出すのは、怖い。だけど、ひとりで抱え込むのなんて、無理だ。 だからそう、告げたのに。 「今頃?」 いっそ淡々と問い返されて、憮然とする。勢いのまま、ルックの方を視線を向けるも、彼は未だに石板を見つめたまま。 「―――覚悟」 「えっ?」 「覚悟、してたんじゃないのか」 愕然とした。 ようやっとこちらに向けられた翡翠が、何も言い返せないまま立ち尽くす僕を容赦なく射る。 「あんたの親友とやらは、一生のお願いだと言ったんだろ。あいつの一生がどれ程の重みを持ってたか、今のあんたは知ってる筈だ」 当時は知らなかったとしても、今は違うだろう、と。 「その重みに押し潰されるのも、愚痴るのも、己を哀れんで泣き暮らすのも、あんたの自由だ。だけど、ソレに振り回されるな」 周囲の者が迷惑すると、情け容赦ない毒舌。 「選んだのは誰でもない、あんた自身だよ」 「解ってるよ。解ってるから……逃げない」 拳を握り込んで目の前の翡翠から目を逸らさずに、誓う。 今の僕にとって、その翡翠に誓うことこそ当然のように思える。この瞳だけは、最後まで僕を見届けてくれる。 逸らされず暫し見合ったままの視線。それはやがて、小さく肩を眇める所作と共に、僅かながら険を落した。 「……どう転ぶにしても、」 心持ち眇められた翡翠は、変わらず自分に向けられていたけど。 「同情なんて無意味な事しないよ。そんな感情は結局、ただの自己満足でしかないじゃない。あんたの痛みはあんただけのものだ。哀しむのも悔しがるのも、当人にだけ許されてしかるべくじゃない? まあ、どうしてもして欲しいって言うんなら、考えてあげてもいいけど」 何時にも増して激しい毒舌。だけど、ちゃんと考えれば正論だって解かる。それに、言葉の節々からも窺い知れるけど、彼は認めてくれてる。 哀しんでいいんだって。 泣いたっていいんだって。 それは、当たり前なんだって―――。 簡単なようでいて、自分にとっては至極難しいそれらを、さもあらんというように許してくれる。 彼のそんな強さと、そうとは悟らせない優しさに……惹かれた。 そう自覚したら、楽になった。 今更だけどね、と目の前の翡翠から視線を外さずに覗き込む。 「何にしても、逃げるのだけは止めることにした」 真の解決はそれでは無理だから。 「逃げても向き合っても同じ苦しいんだったら、前向いてる方が建設的だよねって」 ルックがそう僕に教えてくれた。 それにね―――と。 「ルックの眼を見返す事が出来なくなるのだけは、嫌だなって」 そう思ったんだよと告げる。 いつでも逸らされる事のない、翡翠の瞳。 強く、こちらの内までもを射抜くかのようなその瞳に映されて、恥じる真似だけはしたくない。 「だったら、」 冷たい翡翠が、じっと見上げてくる。 「もうちょっと抑えられるようにならないと」 「気付いて…た?」 「解らないとでも思ってるの」 酷くざわついていた、と。 告げられて、ルックが戻ってくる直前の恐怖をまざまざと思い出した。 大丈夫、今は……ルックが傍に居る。深い呼吸ひとつで、全てを抑え込む。 「錯覚かな、って」 「確かに、それ自体の暴発じゃなかった。あんたの揺れに流されかけた感じだったけど」 「僕の、揺れ?」 「どちらかっていうと、そっちの方が面倒なんだよ」 真なる紋章の多くは、常に主核を乗っ取ろうと隙を狙っている。そして時折、暗の部分の増幅を促す。耐え切れないものは、取り込まれるのだ―――と、告げてくる声音は酷く淡々として。 「ソウルイーターは、特にその傾向が強い」 そう考えれば、前の宿主は厄介な紋章をよく御していた方だろうねと繋げられる。 「テッド……」 本当に、凄いヤツだったんだ。永い刻を、たったひとりで歩いて。 どうして、そこまで強く在れたのか。 そっと、人前では外すことのない手袋へと視線を移す。窺い知れずとも、此処に神はいる。そして、大事な人たち…が。 左手で、更にぎゅっと見えない神を覆う。 「言っとくけどね、僕はそれに呑まれたりしないよ」 唐突に告げられた言葉に、弾かれたようにルックを見つめる。 「………呑まれない?」 恐る恐る訊ねれば、 「当然だ」 と言い切った。 「呑まれるには、呑まれる側の意識が強く作用する。どんなに、それが欲し様と…宿主が望もうと、僕がそれを真に望まない限りそれに獲り込まれることなんて有り得ない。もし仮に、呑まれるのを望んだとしても、僕のこの身を構成する風がそれを容易く許しはしないよ」 だから、有り得ない―――強く断言される。 「だけど、」 「それに獲り込まれるのは、それを望んだって事だよ」 そこに眠るのは、ただひたすらにあんたを想い続けた人々ばかりだろ、と。 「僕はそこまであんたのこと、想ってやしないんだから」 だから、天魁の星があんたにある限り僕を利用すればいい。 そう、きっぱりと言われて。 胸に走った痛みが何なのかなんて……気付きたくない気がした。 …… to be continue |
back ・ menu ・ next