|
ひとつの国のひとつの区切りが、音を立てて訪れる。 何者にも屈しない、何事にも膝折らない―――そうして、最後まで星を担い続けた少年は、 「諦めたくなかったんだ」 そう、呟いた。 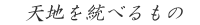 − 8. 終りと焉り − 何度も参加を拒否し続けたにも関わらず、石板の間への誘いの声は絶えることがなくて。渋々ながら、屋上へと移動した。 少なくはなく失われた命への別れと弔いの意と。そして、誓いの想いもあるのだから、と促されたけど、そんなの僕にはよく解らないから。 「やりたい奴等だけでやってやればいい」 送られる方にしても、送る方にとっても、その方がいいと思う。 弔いを兼ねた宴席のざわめきは、酷く遠い。 煩くて、鬱陶しい―――普段なら煩わしいだけのこんな喧騒も、たまになら……嫌いじゃない。こんな時なら、いいんじゃないかと思う。 星の任を解かれた僕は、明日には此処を去る。あの、師と僕しか存在し得ない空間に戻る。 此処に否応なしに連れて来られたときは、さっさと帰りたいと思っていた。 四六時中人の気配が絶えることのないこの砦から、開放されたいと―――そう、ずーっと思っていた。 それも、明日には叶う。 雲もない夜空を振り仰げば、満天の星々が散りばめられていた。音もなく、風が髪を攫う。 ひとつ、瞬いて。 ゆるりと屋上へと続く階段へと視線を向ければ、 「……よ、かった」 ぜぇぜぇと乱れた呼気も露な、そいつの姿を視界に捉えた。 「何、何か用?」 いつもと変わらない問いを口にすれば、乱れた呼吸を整えていた顔がくしゃりと歪む。そんな表情を見て、こいつ自身が気持ちの上で星の任を解いたことを知る。 「……あぁ、終わったんだね」 告げられる前に淡々と呟くと、その顔が泣き笑いのそれにとって変わった。 「世界は哀しみに満ちている」 それを呟いたのがこの男でなければ、それ程に驚きはしなかったけれど。 「何、それ」 「うん、そう思ってた時期もあったなって?」 そう言って、にこりと笑うのを見て何故だか僅かながらに強張った肩が落ちる。 「今は違うって?」 「そうだね、淀んだ悲しみの中に居た僕に光を届けてくれたのは、ルックだよ」 「………は?」 「だから、その光を追った。そしたら、急に視界がクリアになった。周りを見たら……優しい人たちが居て、そして見守ってくれてるのが解って」 きっと、彼らに僕が必要なのではなく。 僕に、彼らが必要だったんだ。 彼らは、その為の星々だったんだね。 そう微笑みながら言い切るのに、目いっぱい呆れた。 「又、えらく建設的な考え方だね」 「それもこれも、ルックのお陰」 そんな様を見て。 人の強さを思い知る。 こいつは、何を得何を失ったのか。 得たものを欲していたとも思えないし、ましてやそれ以上に失ったものの重さなんか、想像も付かない。 それでも、こいつはこうして笑っていて。 こいつのそんな強さは眩しくて、数多の者を惹き付けられずにはいられないんだろうけど。 だから、目を細める。 僕の求める強さと、こいつの見せる強さは違うものだから。引き摺られる訳には、いかない。 「だから、僕は行くよ」 だけど、その決意は酷くこちらを揺さぶる。 「僕にはまだまだ、しなきゃならないことがあるし」 心持ち強まった視線が、その右手の甲に向けられている。そんな様に、改めて覚悟を決めたのだと、知る。 「ようやっと覚悟が出来たんだ」 真を宿す、イコール主ではないのだ。 生と死を御しきることが出来なければ、真の主とは認められない。 大き過ぎる力を抑えきれず身諸共に心を壊すのが、普通といっていい。 だけど―――こいつがその身に宿すのは、友の願いと近しい人々の想いで。大切に思い、大事に思われたという事実は、これ以上もない強さに繋がるんだろう。 だから、きっと、こいつなら御しきれるんじゃないかと思う。 「こいつと離れる訳にはいかないから」 出来るなら、最後にしたい―――こんな想いをする人を出さない為に。 小さく零れた言葉は、偽りのない本音だったろうけど。 まだまだ、甘い。 こいつは一体いつまで、そんな風に考えていられるだろう。 自分の考えの甘さを思い知るときが、必ずくる。 少しでも、それが後のことであることを祈ってやるくらいはしてやってもいいけど…と考えている己に気付いて自嘲する。 甘いのは、僕も同じか。 「それに、」 ひたりと、こちらに据えられる黒曜の瞳。 出逢ったときと変わらないように思えるそれは、真っ直ぐとこちらを射抜いてくる。 「これは、僕と君を結んでいるよね」 思いもよらなかった台詞に、瞬時思考が固まる。 「それって、ルックと又、逢えるってことだよね」 一体、こいつは何を言ってるんだ。 「その為にも、僕はこいつを抑える術を身につけたい」 何を、望んでいるんだ? 「……訳、解んないよ」 台詞の端々に込められてるんだろう言葉の真意がこれっぽっちも読めない。 別に、解らなきゃ解らないままでもいいんじゃないかとは思いながら。笑顔の裏で何考えているのか図り得ないこいつの場合、そうするのも躊躇われる。 出所も確かでない微妙な危機感に苛まれて仕方ないのだ。 「……解んない、かな?」 頗る解りやすいと思うんだけど、と首を傾げる姿は困り果てた子供のよう。 そんな様見せられても、解る訳ないし。どうにも不可解極まりなくて訝しさをそのまま表情に乗せれば、深々と溜息を零された。 「何だっていうのさ」 溜息を零したいのはこちらだ。いつになく、理解不能なヤツに成り下がってる気がする。 「ま、そっちはおいおいにしといて」 小さく呟かれた台詞を聴覚が捉えた刹那、にこりと笑みが向けられ。 「僕は、ルックに呪を掛ける」 「………へぇ」 瞳を細めて目の前の黒曜にひたりと向ける。 面白い。この僕相手に、いい度胸してるじゃないか。 「―――あのね」 こちらのそんな視線をものともせず、何とも場違いに相手の表情が蕩けたのを見、訝しさに眉根が寄る。 「君が……好きだよ」 「は?」 「ルックが、好き」 好きって、何。 好意を伝える言葉? だけど、それ以上に。相手の視線を、心を留め縛り付ける。確かに、それは呪いといえなくもない。 ―――冗談じゃ、ない。 「必要ない」 そんなの、僕には理解できない。 したいとも、思わない。 こんな呪いは、要らない。 この世界は、要るものと要らないもの。そして、どうでもいいもので構成されている。 こいつのいう好きという感情をその中にあてはめるのなら、要らないものだと即断出来る。 なのに、そうはっきり告げたにも関わらず。 「どうでもいいって言われなくて良かった」 そんな風に、ほっとした表情を向けられて。 「どうでもいいって、思考にこれっぽっちも乗せられることもなく、歯牙にもかけられてないってことでしょ」 だったら、要るか要らないか、選別の土俵に一度でも上げられた方のがいいに決まってる、って。 「……そういう基準って、どうかとも思うけど」 前向きなのか、後ろ向きなのか、微妙に判断付きかねる考え方だ。 「何が起こるか解らないのが世の中だよ」 「天変地異が起こる確立並に、まずないけどね」 そう呆れ気味に言えば、至極嬉しそうに笑う。 「天変地異くらいなら起こせそうな気がする」 「……ちょっと、待て」 こいつが言うと全くの冗談に聴こえないから、性質が悪い。笑顔でやってのけそうな気がする。 「…………これ以上、面倒起こすな」 今だから思うのかもしれないが、星の役割としての任はそう気を負うほどのものではなかった。何より大変だったのが、天魁の星のお守とフォローだ。 「あんたに星が降りる事は、二度とないんだから」 そして、星の任が解かれた今、面倒見る義理はないんだ、とはっきり告げたにも拘らず笑みは深くなるばかり。 「これからは、星なんて関係なくルックとの関係が築ける」 関係って、何? 確かに、真なる紋章に時間を握られている限り、同じ時を歩んでゆくんだろうけど。進む先が違う僕らの道が、交わることはあるんだろうけど、添うことはないっていうのに。 「……なんでそこまでおめでたいのさ」 呆れ返って、開いた口がふさがらない。 「好きだから」 返答になっているのかどうかさえ解らない言葉を返されて、僅か眉間を寄せる。 「諦められないんだから、そうなるしかないかな…って」 「……あんたのその理論は、全くもって理解できない」 「そうかな?」 「ま、感情的にはそうなのか、って思わなくもないけど」 人が人たる所以ではあっても、結局、感情ってやつは理論でなんか語れない部分が多いから。だからこそ、厄介でもある。 刹那、驚きに瞠られた黒曜が次第に柔らかに笑んだのを目にし、 「だからって、あんたを許容するとかいうのとは、違うから」 一応念を押しておく。 これ以上、思い込みでこっちのペース崩されちゃ堪らない。 だけど、解ってるよと頷いたその表情は、やっぱり穏やかに微笑んでいて。 何故と考える間もなく、視線を逸らしてしまった。 「ーッ、」 本当、調子が狂う。 こいつといると、不本意なことばかりな気がする。 そんな僕の不自然極まりない態度に気付いているんだろうに、耳に届いたのは、声音こそ柔らかだけど今までの空気を塗り替えるものだ。 「僕らは、前を向かなきゃならないんだよね」 紋章の意のままにならない為には。自我を尊ぶ為には―――そう言って、静かに笑うから。 生と死に屈せず手折られずに在れたこいつという存在、そのものに。 「…………」 漠然としない心持ちながら、それでもその内は凪いでいて。そうと意識しないままに目が細まった。 「解ってれば、いいんじゃない」 うん、と頷く。そんな素直な様に訝しさばかりが湧くも、突付けば頭の痛くなる言葉の応酬が待ち構えているのは必須だったから。 窺うような視線だけを向けた。 と、じっとこちらを見据えた黒曜石の瞳に射抜かれる。こちらの内まで見抜くかのようなその瞳は、居心地の悪さばかりを助長させはするが、逃げ出すなんて選択肢はこれっぽっちもなく。負けじと、睨み付ける。 暫し視線を交し合った後、何の前触れもなく黒曜は柔らかに蕩けた。 「行くよ、」 留まってちゃ、ルックの前には立てないから、なんて軽口をほざきながら。 「ルックと再び逢う為、と……傍にいてもいいって思ってくれるように」 頑張るね、なんて告げられたって、望んじゃいないそれに他に何て返せばいいのか解らないから。 「……いいから、さっさと行けば」 月影が移動しているのを目にし、そのまま空を仰ぐ。 位置を変えた夜の空は、時の移ろいを示す。 「いい加減、主役の居ないのに気付かれるんじゃない」 「それはゴメンだな」 出立できなくなる、と苦笑と共に零す。 生まれ育ったこの国を、護ろうとして戦い続けたのだ。その結果、失ったものがこいつの全てだったのだとしても。それでも、去りたくてそうするのではないことくらい知っている。 これから、どんな風にこの国が変わってゆくのか。 その先で、人々はどんな笑みを見せるのか。 見ることが出来たかもしれない、その担い手のひとりになれたかもしれない。 ―――その身に真さえ、宿らせていなければ。 だけど、そんな仮定になんて意味がないから。 「行ってくる」 「………精々、頑張れば」 届かなければそれでもいいと呟いた言葉は、だけれどしっかと拾われたようで。 「ありがとう」 感謝の意と共に向けられたのは、泣きたくなるほどに綺麗な微笑みだった。 振り返ることなく去って行くのは、少年の域をようやっと過ぎた大きくはない背。 ただ、掛ける声もなくじっと見送る。 あいつの選んだ道は生半可なものじゃない。 此度の戦など比にはならないくらいの苦しみが、その先に待ち受けていないとは限らない。 得たものを失うのではという恐怖は、常に付き纏うだろう。 失ってしまった過去の痛みに、胸を苛まれるだろう。 それは、予感ではなく、事実だ。 だから―――旅立ちの、今くらいは。 ひとつの結末を迎えた、束の間の安らぎを。 意識を集中し、ゆるりとてのひらを翳せば、嬉々として収束してゆく風を感じる。 「星の任を終えたあんたへの、最後の餞だよ」 決意を秘めたその背に、そっと追い風を送った。 夜空を振り仰ぐ。 次に星が集うのは、何年、何十年後か。 たったひとつはっきりと解っているのは、これで終わりではないのだということ。 ただ、それだけだった。 …… to be continue |
back ・ menu ・ next